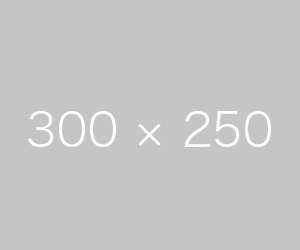上質な絹を使った昔の着物って、今ではもう目にすることがなくなってきました。絹を作るための養蚕農家、糸を紡ぐ人、染める人、織る人など、各工程を担う職人たちが減ってきたのです。
それはなぜか?
時代とともに需要がなくなってきたからです。
ただただ着物文化が失われていくのを見ているのは、とても辛い。
そこで考えたのが舞音なのですが、立ち上げた理由は、着物文化の継承だけではありません。古くなった着物をアップサイクルし、持続可能な産業として地域や社会に貢献にしたい。そんな思いもありました。
じつは、そもそも着物は「長い期間にわたって着るもの」として作られています。子どもの成長や体重の増減に合わせて寸法を調整することができるのです。
直線裁断で作られているため、他の衣服と比べて端切れもあまりありません。ほどけば長方形の反物に戻ることから新しく作り直すことも可能。着物はリユースやアップサイクルしやすい、とてもサスティナブルな衣服なのです。
SDGsで定められた17の目標の12番目に「つくる責任、つかう責任」があります。物をつくる側とつかう側が、持続的に生産と消費を行えるよう、少ない資源で効率よく物をつくって、廃棄物を減らすことを目指さなければなりません。着物の場合、つくり手が減ってきたとはいえ、廃棄される現状に歯止めをかけないといけないと思っています。
「舞音」のファブリックや掛軸、風呂敷が多少なりとも課題解決になれるよう、日々、着物と向き合っていきたいです。
正直、どの形が正しいのか、わかりません。
正解はないと思います。
でも、私の取り組みに共感してくださって、「アリだな」って思ってくれる人が一人でもいてくれたら、モチベーションに繋がります。